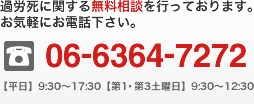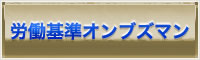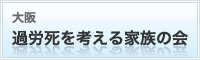過労死事件の支援闘争に取り組んで─土川過労死・廣瀬過労死事件・平川労災認定事件から─ 全印総連大阪地連執行委員長 村上 茂(民主法律272号・2008年2月)
全印総連大阪地連 執行委員長 村上 茂
年間に過労死や過労自殺の件数が3万人を越えるという事態は「映し鏡」で言えば、まともな社会とはいえません。それでも、増え続ける異常さ。そして、残された家族が労災認定などの裁判で何年もかかって闘わなければならないこともまた、輪をかけて異常としか言いようがありません。
私が関わった事件としては標題の通りです( 平川事件は現在も会社を相手取っての裁判がつづいています)。
土川・廣瀬過労死事件は、ともに「若者の過労死」と言う特徴的な事件でした。土川由子さんが23歳、廣瀬勝君が21歳。普通ならば最も青春の華やかな世代を満喫する、好きな人と恋もする年頃、大きな夢に向かって生きて行く途中に、仕事でしかも長時間の苛酷な労働で企業が労働者の健康にはいっさい配慮しない中で「命を奪われた」事件でした。
事件の概要は、土川由子さんの場合、当時の過労死認定基準(発症前1週間の過重性を評価する)の壁があまりにも高く、また会社に対する損害賠償請求訴訟にしても、当時は過労死事案についての民事訴訟や判例が数えるほどしかなく、しかもタイムカードはほとんど打刻していなくて、労働時間や仕事の内容の証拠もないところから始まりました。
廣瀬勝君の場合は、アルバイトとして入社51日目の突然心臓死という事件で若者のひたむきさや向上心を逆手に取って低賃金で極限まで働かせる企業(使用者)のやり方に警鐘を鳴らしたという点で土川由子さんの事件とも共通していました。
両方の事件とも解決に至る道筋は簡単なものではありませんでしたが、困難な中での道筋をつける、全国の過労死運動の大きな流れの中で蓄積疲労による過重負荷を認めた新基準を厚生労働省につくらせたこと、認定基準の改定が幸いをして勝利をしました。もちろん、勝利をしたからといって、亡くなった人が帰ってくるわけではありません。しかし、何よりも原告(お父さんやお母さん、ご家族のみなさん)が悲しみを乗り越えて腹の底からの怒りのもとに先頭に立ってがんばった結果が勝利をもたらしたこと、そして、強力な弁護団、過労死家族の会のみなさんをはじめとした大きな幅広い支援があったことは言うまでもありません。
土川事件、廣瀬事件ともに、労働組合がどのように支援に関わってきたかについて報告をします。土川事件では、由子さんのお父さんが私と同じ職場(高速オフセット)であったことです。大阪労働健康安全センターの総会でお父さんの訴えがあり、その時に同センターの事務局長の北口さんから、「組合が中軸になって、また、全印総連をはじめ関西のマスコミの仲間にも訴えてほしい」との協力要請が始まりでした。
由子さんの一周忌の同日に会社と代表者を相手取って損賠請求を大阪地裁に提訴された翌日に支援の会準備会が持たれ、事務局を高速オフセット労組におくことを確認し、正式に「土川由子さんの裁判を支援する会」の結成がされました。高速オフセットでは印刷産業における鉛中毒、頸腕、腰痛等職業病をなくす運動での蓄積がありましたが、ややもすれば、そうした運動が組合活動家の範囲にとどまっていたことは否めませんでした。土川事件では労働組合が組合員の家族の労災・過労死事件を真正面からどう取り組むのかが試されました。
「支援する会」は、ニュースの発行(題字は由子さんが一番好きだった色『カラーパープル』、通算20号)をはじめ、個人会員、団体会員、署名活動を友だち・家族・デザイナー仲間・同窓生・労働組合・市民団体に支援の輪を広げる取り組み、裁判傍聴への案内、由子さんの生きた証である貴重な作品をポストカードにしての販売、お母さんと一緒に組合の大会や諸団体への訴え、そして同じ過労死事件で闘っておられる原告の支援と裁判の傍聴等々、できることは何でもやろうという取り組みをしました。当然のことながら「支援する会」が独走するのではなく、ご家族のみなさんの気持ちを第一に考え、常に弁護団も含めて連携した活動を続けました。こうした中、マスコミも大きく取り上げられたことが事件の勝利にもつながりました。
廣瀬事件では、土川事件の取り組んだことをベースに、「廣瀬勝君の過労死裁判を支援する会」を全印総連をはじめ関西のマスコミの仲間、働いていた北区の労働者の仲間、そして住んでいた枚方を地盤とする北河内の労働者のみなさん、過労死家族の会のみなさんにも入っていただき結成することができました。事務局は全印総連・大阪地連において、ここでもニュースの発行(題字は「雨ふってたら」、これは勝君とお母さんのやさしい息づかいから採用したもので通算10号)、そして、署名や団体・個人会員の拡大と署名、裁判傍聴の案内、被告の会社前の定期宣伝行動(ビラまきやハンドマイク)や申し入れ、原告と一緒にあらゆる場所での訴え、他の裁判傍聴や支援等に取り組みました。ここでもマスコミが大きく事件を取り上げてくれました。
平川事件は、世界に冠たる大日本印刷の子会社での苛酷な勤務のもとで自宅で倒れ、外傷性頸髄損傷を負い、現在も不全四肢麻痺の後遺症のもとで会社を相手取って裁判を闘っておられます。ここでも同じ印刷労働者として「平川さん訴訟を支援する会」の一員として署名や裁判傍聴や署名に取り組ませてもらっています。
過労死事件(過労自殺も含め)の被害者が多くは労働組合に組織されていない労働者であるという反面、れっきとした労働組合がありながらこの問題に真正面から取り組まないという弱点があります。そのことが、企業(会社)をして個人の責任に帰するという、まさに企業としての健康と安全配慮義務を怠り、理不尽な結末を迎えることになっています。最近のトヨタの内野事件もそうであるように、いくら立派な会社でも働く者を犠牲にする会社、誤解をおそれずに言うならば「人殺し」企業にに人間の尊厳を語る資格がないと言えます。
過労死事件の請求や訴訟の件数と認定される件数との開きはまだまだ大きく、行政の壁を突破する闘いはこれからも続き、何よりも過労死・過労自殺事案をつくり出さない社会、家族も含めた「働く者のいのちと健康を守る」課題を大事にした労働組合の役割がますます大きくなってきています。
(民主法律272号・2008年2月)
2008/02/01