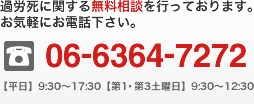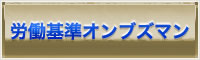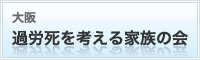印刷会社主任の過労死事件で勝訴 弁護士 佐藤真奈美(民主法律時報412号・2006年10月)
弁護士 佐藤真奈美
1 事案の概要
広告宣伝物等の印刷会社(社員数は役員を除いて4~5名)で主任として働いていた男性(昭和48年生、被災時30歳。以下「被災者」)が、平成15年6月、虚血性心疾患で亡くなった。被災者は、ほとんどの日の帰宅時間が午後11時を過ぎるなど、非常に忙しく、平成15年6月末で会社を辞める決意までしていた。生前の被災者の様子を見ていた被災者の妻は、過労死としか思えず、京都下労働基準監督署に労災申請した。しかし、時間外労働時間がいわゆる過労死ライン(被災前6ヶ月平均80時間以上)に達しないというのを主な理由に、業務外決定が出された。審査請求も認められず、平成17年5月、大阪地裁に提訴した。
大阪地裁第5民事部合議1係(山田陽三裁判長)は、平成18年9月6日、原処分を取消す原告勝訴の判決を言い渡した(被告は控訴せず確定)。
2 事案の特徴
労災申請時、原告の手元には労働時間についての資料は何もなく、原告は、自分の記憶を辿って被災者の半年間の帰宅時間をまとめ、労基署に資料として提出した。また、「いつも締切に間に合うよう追われている」「トイレに行く時間ももったいない」「1文字まちがえただけでも全て印刷を刷り直しになり、何百万円・何千万円の損害となる」など、被災者が仕事について訴えていたことをまとめ、労基署に資料として提出していた。
会社にタイムカードはなかったが、出勤簿(社員の出勤・退勤時間について、専務が手書きで記録するもの)が残されていた。労基署は、その出勤簿をもとに、時間外労働時間について、被災前6か月の平均が75時間25分であったと認定していた。要するに、被災者の時間外労働時間は、過労死ラインに、たった4時間35分、足りなかっただけなのである。しかし、労基署は、時間が足りない点をとりあげ、労働の質的過重性をみることなく、業務外との判断をした。
3 訴訟での主張
訴訟では、被災者の時間外労働時間は労基署の認定より長かったと考えられること、主任という立場から他の社員に比し過重業務であったこと(労働時間の比較)などを主張した。労災申請段階から、退職した元同僚の協力が得られていたことから、元同僚の陳述書も提出した。
これに対し、被告は、被災者の業務に起因するストレス等について、①被災者は他の社員に比べ作業に時間をかけるタイプだった、②同僚や上司は被災者が担当する業務が特に過大と言えないと述べている、③被災者は十分な休養をとっており疲労は回復していた、などと反論してきた。
4 裁判所の判断
裁判所は、まず、業務起因性の判断について、司法上の判断にあたっては認定基準に羈束されるものではなく全証拠を総合検討し判断すべきことになると判示し、労働時間以外の事実についても細やかな検討をした。そして、労基署が認定した時間外労働時間について「争いのない時間」として認定した上で、多岐にわたる業務に起因するストレス(納期の存在や多大な損失の可能性、責任者としての立場など)を指摘し、業務の困難性、業務から生じるストレスの度合いにおいて相当程度過重性のある業務を遂行していたと判示した。さらに、被告の主張については、①労働時間が長かったのは、労働効率が低いからではなく、業務の困難性等による、②業務の内容や立場の差を考慮すれば、他の同僚の供述から業務の困難性が同程度とはいえない、③確かに被災者は休日を取得しているが、恒常的な長時間労働などで疲労の蓄積が生じると考えられるところ、その程度の休日では蓄積された疲労が解消されるとは考えられない、として排斥した。
判決の中では、原告の供述などを引きながら細やかな事実認定がなされており、「(被災者は)パソコンや仕事上の知識が高く、真面目に仕事に取り組むがんばり屋でもあった」といった判示に象徴されるように、非常に人間味のある温かい判決であった。
5 本件の意義
脳・心臓疾患の過労死事件では、時間外労働時間が過労死ラインに満たないことを理由に、業務の質的過重性はほとんど考慮されることなく、業務外決定を出されるケースはままある。本判決は、そのような機械的運用に、警鐘を鳴らすものといえよう。
原告は、被災時29歳、生後6か月の長女と二人だけの生活で、どれだけ不安だったかと思う。彼女がよく「自分が裁判をやってるなんて、信じられないです。」と言っておられたのが、とても印象に残っている。夫の死に直面し、「過労死としか思えない」という実感から立ち上がり、勝訴判決が勝ち取られる。こういった積み重ねが、過労死のない社会につながっていくんだろうと感じる。その積み重ねのお手伝いを、ずっと、していきたいと思う。
(弁護団は、大橋恭子弁護士、佐藤です)
(民主法律時報412号・2006年10月)
2006/10/01