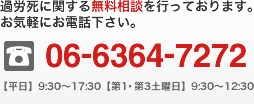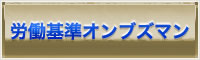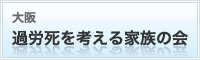職場の長時間労働「規制」に関する提言 大阪労働健康安全センター事務局長 北口修造(民主法律233号・1998年2月)
大阪労働健康安全センター 事務局長 北口修造
1 職場での時間外労働の規制
昨年、手元にした過労死事案及び頚肩腕障害事案の共通性は、長時間にわたる時間外労働と過密労働がその要因をなしている。また長時間労働・過密労働は所定内労働時間内での「適正な作業人員」(労働者の求める)が確保されていないところに大きな問題点を残していることかいえる。
現行法規のもとで次の諸点について考察してみたい。
労働省告示「労働基準法第36条の協定に定められ一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」第3条(一定期間についての延長時間に関する目安)が労使間、とくに労働組合の側として「次の各号に掲げる事項を十分考慮するように務めなければならない」との条項をどう理解しているのかをまず触れてみたい。たしかに、この条項には「罰則」規定は定めていないが、時間外・休日労働に関しては、労基法第36条は 「当該事業場に、過半数で組織する労働組合…労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし…これを行政官庁に届け出た場合…その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」要するに、労使の代表者による「協定」かなされなければ「時間外・休日労働」ができないことにある。問題点を、敢えて言えば労働組合側が時間外労働に「受け身」 になり、使用者側の要請を鵜呑みにし、厳密に対処していないところにある。
事業場に働く労働者の中には、所定内労働の賃金では生活を維持できない、一定の残業時間を求める声も否定できないことば事実である。それら一面の要求を仮に受け入れるにしても「指針の一定期間」(1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間、1箇月45時間、2箇月81時間、3箇月120時間、1年間360時間)を各所属する労働者の意見や要望も聴かず、また組合執行部で緻密に検討もしないで「目安時間」を無原則的に協定化をしているのである。目安は上限でありそれを如何に下回る規制措置をとるか、労働者のいのちと健康を守る視点に立った規制が求められるべきである。
もう一つは、事業場労働組合(又は単組)まかせでなく、産業別(単産)組合の役割と機能にある。産業別組合が、実態把握と合わせて時間外労働・休日労働に関して「統一要求」を設定しているかにある。それも「法定内」でなく、法定外としての設定である。昨年4月から法定内週40時間労働制(教職員週44時間、小規模の商業・映画・演劇・接客娯楽業週46時間)と言えども、年間2080時間以上が時間外労働として定めており、休日においても、週1日、4週4日であり、「目安」時間外労働と、さらに別途休日労働を加えると膨大な労働時間となる。このことからして、法定外(例・所定内1日7時間労働、以上の労働時間は時間外、週休2日制の場合、その休日1日の労働は休日労働)と定める意味は大きい。時間外・休日労働の縛りを単産の統一基準の骨格とし、1日、1週、各週、1箇月、年間と、それらの時間外労働時間数を設定し、協定期間を1箇月単位に区切り、いつでも見直しできる状態にあるべきである。
過労死事案の中で、公務職場は全く時間外労働に関する労使協定は見当らない。運輸業では未組織労働者であり、指針の目安時間外労働時間は適用除外であるが、しかし労基法第36条の協定が不明となっている。また販売・サービス業においては目安時間をそのまま1年間協定をしているが、実態は協定した時間外労働時間を遥かに超過し、そのもとで労働者は生命を奪われている。なぜ労働組合としての毎日・毎週・毎月チェックをしないのか。労働組合としての一端の責任を問わざるを得ないのである。
平岡過労死事件の時、息子さんは 「労働組合ほ死んでいる」と言った。千葉県労連の支援をうけて労災認定を勝ち取ったS労組の委員長は「労働組合として恥ずかしい2度と過労死を出させない」と決意を表明した。連合M電器労組では60年代から交わしてきている時間外労働36協定に「違反した場合、直ちに協定を破棄」する条項を厳守させ、労働組合としても毎日点検にあたっている。労働組合は冠だけで評価することばできない、大義名分を語るもいいが、真面目で、まともな労働組合として、職場を直視し、労働者・組合員との連帯、労働者の生命と健康を守る課題を日常的に視野に入れた活動をしているかが労働組合に対する評価の一指標でもある。
2 公務労働者も労基法36協定の適用下
公務労働者の中でもとくに指摘すべき事業場は、教育職場の学校と保育職場ではないだろうか。頚肩腕、腰痛の発症は保養H所・養護学校の職場で多発している。また過労死においては学校現場で発生している。労基法の最低基準である休憩時間(労基法第34条)も唆味であり、保障されているとは到底言えるものではない。まして時間外労働に関しては、無協定の状況下で時間外労働がなされている。労働安全衛生法にいたってはまさに無法職場である。
なぜ労基法36条か守られていないのか。地方公務員法第55条②「団体協約を締結する権利を含まないものとする。」に目を向いて、労基法36条も含むものと考えられていた。しかし、地方公務員法第58条(他の法律の適用除外)の各号を見ても労基法36条は適用除外にはなっていないのである。
この間題について、「地方公務員にも36協定締結権がある」-なぜ・目治省は違法な残業を放置してきたかー(「赤旗」特集版・1992・6・15・諌山博)の論文にある。当時参議院議員であった諌山氏は、参議院地方行政委員会で自治省公務部良に・目治省内部資料に基づいて確認を求めたものである。要点のみを列挙すれば、①時間外労働させるのは労基法第33条3項「公務のために臨時の必要かある場合」②「臨時の必要」がなければ時間外労働させることはできない③「臨時の必要」がない場合には、民間の事業所と同様に労基法第36条による協定を結べば時間外労働をさせることかできる。(資料は字数の制限で省略)これほど明解にもかかわらず、今尚、無協定のまま時間外労働が罷り通り、その結果、疾病に苦しめられ、時には生命も奪われいるこの事実・実態に目を背けることはできない。目前の違法状態の放置は、事業場単位の労働組合の「機能の麻痺」「休眠・休業」というべきなのか、それとも「怠慢」と言うべきだろうか、産業別組織の指導も問われている。
3 「規制」を主眼とした労使協定の位置づけ
これまで労働法制の改悪、なかでも労基法「改正」条項は、日経連の要請に応えて労使自治の名のもとに「労使協定」が各条文・条項に挿入されている。とくに「変形労働時間制度」の導入は、一箇月単位の変形労働時間制(労基法第32条の2)除いて、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、事業場外労働・裁量労働(労基法第38条の2)は労使による書面の協定となっている。
いま、規制緩和による労働法制の全面改悪か企図され、これらの演題に対する一部の学者・研究者の講演又は談話を視聴する際、労働組合が果たすべき役割が主として反対運動のみに強調されがちになり、そのことば当然であるのだが、他方、労働組合が職場で「どう規制・反対」していくべきかについては、触れようとしていない。
前項で労基法第36条の時間外・休日労働の規制について述べてみたが、この点に関しても、一部の学者の中には「時間外労働の協定をすれば何時間でも働かせることかできる」との一側面のみを主張し、労働組合として時間外労働協定拒否又ほ協定を通して時間外労働の一定の規制、人員増及び割増率の引き上げ等の側面についての視点を見失っていると指摘せざるを得ない。
労働組合は団結権・交渉権・行動権を保持し同時に協約締結権を擁しているのである。労使の協定・協約は、使用者側の一方的、強行・強制的な行為を規制するばかりか、労働者の権利を擁護・拡充にとって極めて重要である。その意味において、労働組合として 「労使協定」をどのように位置づけをし活用しているかが問われているのである。変形労働時間制度の「導入」は、労働組合が協定に応じなければ導入されない。このことをます明確にしておくべきである。仮に導入に譲歩する際においても、①業務の種類②該当労働者数③変形期間(起算日)④変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日⑤変形労働時間制による対象期間等(以上、様式第4号)について、各職場の徹底した討論のもとに集約して対処すべきである。
これまで時間外・休日労働の協定化においても、①時間外労働させる必要のある具体的事由(休日労働も同文)②業務の種類③労働者数(男女計)④所定労働時間⑤延長することができる時間(一日、一日を超える一定の期間)⑥期間(以上、様式第9号)のもとに、各職場で論議をなされて集約されたものなのか疑問である。指針の第2条(業務の細分化)、第3条(一定期間)についても検討を要するならば、決して全ての労働者が対象でなく、まして一年間協定(時間外労働の常態化)に陥ることはありえないと言うべきだろう。職場労働者から遊離した代表者(専従役員)の個人判断による署名・調印は禁物である。
変形労働時間別の中で、1箇月単位の変形労働時間制のみが公務労働者も適用下にある。とくにこの変形労働時間制のみが本法で労使協定なしに就業規則の改訂で実施できることになっている。だが、「改正労働基準法の施行について」 (平5・4・1基発第229号)では、①1日、1週間の労働時間の限度(1日9時間、1週間40時間/教職員44時間)、②始業及び終業の時刻の定め③就業規則変更届の受理に当たっては労働者代表の意見書をチェックし、必要に応じてその意見を十分聴くよう指導する等的確に指導すること。
この通達では、従来の就業規則の変更届、形式的扱いでないことを認識しておくことが重要である。
最後に、事業場で労働者の過半数を組織していない場合、あるいは未組織である場合における過半数代表の選出の問題である。「労使協定の締結の適正手続」(昭63・1・1基発2号)として、次の要件に該当するものとして①過半数代表者の適格性として、事業場全体の労働時間等の労働条件の計画・管理に関する権限を有する者など管理・監督者ではないこと。②選出方法として、使用者の指名などその意向に沿って選出するような者でないこと。過半数の労働者がその者を支持していると認められる民主的な手続がとられていること。すなわち、労働者の投票、挙手等の方法により選出されること。
なお、事業所内複数組合においては、「規制」を前提に据えた労組間協議も検討課題として言える。
(民主法律233号・1998年2月)
1998/02/01