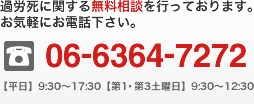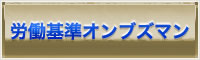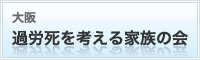36協定の情報公開訴訟判決とその活用 弁護士 松丸正(民主法律263号・2005年8月)
弁護士 松丸 正
一.過労死の温床である三六協定
厚労省の過労死の認定基準は発症前1ヵ月間(30日間)で週40時間を超える時間外労働が100時間を超えるか、発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間のいずれかの月の時間外労働の平均が80時間を超えるときは、業務と発症との関連が強いとして原則として業務上と判断している。
一方、三六協定についての限度時間を定めた厚労省の告示は月45時間、年間360時間などの時間外労働の限度時間を定めている。
従って、事業所ごとに労使間で締結される三六協定が厚労省の告示の限度時間を遵守し、告示には法的拘束力はないという限界はあるものの届出にあたって適切かつ強い指導を行い、かつそれが職場で実行されていれば月の時間外労働が80時間、更には100時間という長時間労働は生じるはずはなく、過労死は死語になるはずである。
では過労死が生じた職場では、三六協定を無視した(労基法違反として6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となる)労働が行われているのだろうか。
ある過労死事件のなかで、会社と交渉した際に被災者の遺族の代理人として三六協定違反の有無を追求した際に、「当社では三六協定違反行為はない」として示された三六協定には「特別な事情があるときは年間900時間まで延長できる」と記載されていた。
このように大企業を含めて、多くの会社では告示の限度時間以内にとどめた一般協定とともに特別の事情があるときは、更にこれを延長して時間外労働をさせることができるとする特別協定が締結されている。職場のなかでは、特別協定で定められた限度時間が、時間外労働の限度時間と考えられているところが少なくない。
特別協定の限度時間を調べてみると、年間960時間(月80時間)、更には1200時間というものが見うけられ、1800時間という常軌を逸したもの(病院の医師)さえある。このような明らかに過労死ラインを超えた三六協定が労使間で締結され、かつ労基署もこれを受理しているという実態が過労死事件に取り組むなか明らかになってきた。
二.情報公開請求訴訟の提訴
時間外労働の限度を画すはずの労使の「合意」による三六協定が、賃金不払労働(サービス残業)と並んで過労死の温床となっているとの認識から、労働基準オンブズマンは三六協定の実態を明らかにすべく、大阪労働局長に労基署に届出られた三六協定の情報公開請求を行った。しかし、事業所名は非開示(黒塗り)となった一部開示しかなされず、どの会社のどの事業所のものであるかは判明しなかった。それが開示されないことには具体的な企業名・事業所名を指摘して、労基署・労働局を通じてその是正を求めさせることはできない。
そこで平成15年7月24日、大阪地方裁判所に対し、情報公開請求をした高本知子弁護士を原告、大阪労働局を被告とする情報公開請求を提訴した。
三.訴訟の争点と勝訴判決
争点は①公にすることにより当該事業者の権利競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるか(情報公開法五条二号イ該当性)、②公にすることにより国の機関等が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるか(同法五条六号該当性)、との2点を中心に争われた。地裁判決(平成15年(行ウ)第67号、平成17年3月17日判決)は事業場名の開示はいずれも該当しないとしてその開示を明示、労働局長も控訴せず断念した。
四.判決を活用して
労働基準オンブズマンでは、この判決を得て、早速国内の主要企業である「日経五〇〇社」の各社の本社における三六協定について、東京・大阪・愛知をはじめ全国各地の労働局に対し情報公開請求を一斉に行い、その開示を得つつある。
大企業にも拘らずと言うべきか、大企業故にと言うべきか、既に開示された三六協定の多くは特別協定条項を定めており、過労死ラインの月80時間(年間960時間)を超える時間外労働を容認するものが多く見うけられる。時間外労働の枠と別に休日労働については無制限という協定も多く、時間外労働と休日労働をあわせた時間数は更に上まわることになる
労働基準オンブズマンとして今後情報公開させた三六協定を分析したうえ、厚生労働省・各労働局に対し、事業所の三六協定を受理するにあたっては限度時間の告示を厳守させ、特別協定条項は原則として認めさせず、受理しないことを申し入れる予定である。
またホームページ上に、過労死ラインを超える三六協定を締結している企業名・事業所名とその内容を公表するとともに、その是正を過労死予防の視点から求めていくことも検討している。
三六協定をめぐっては、過労死が生じやすいはずの「新技術・新商品の開発」に従事するものはその限度時間の対象にならないなど、問題点が多くある。更には管理監督者はそもそも労基法の労働時間規制の対象外とされ、かつ管理職=管理監督者という誤った労基法の認識の下で、課長更には係長クラスでさえ三六協定による限度時間規制の対象外との職場の「常識」がまかり通っている。
例外的にしか認められない特別協定による限度時間が、日常的な時間外労働の基準と多くの職場ではなっていると同様、課長は管理監督者だとの非常識(職場では常識なのだが)が、今はやりのホワイトカラーエグゼンプションの議論の底流にはある。
ともあれ労働基準オンブズマンは、職場の労基法無視の非常識さを労基法にもとづく常識によって是正すべく日夜闘い続けているのです。
(民主法律260号・2005年2月)
2005/08/01