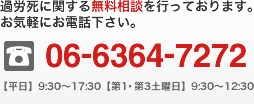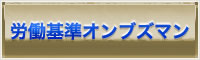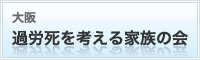サービス残業代の支払い─井島事件 弁護士 佐藤真奈美 (民主法律252号・2003年2月)
弁護士 佐 藤 真奈美
一 二〇〇二年一一月二二日、未払いサービス残業代の支払いを求め、民事訴訟を提起した。
1 事案の概要
原告は二九歳の男性。被告会社(関西電力の子会社、電気絶縁油の製造や電気工事を主とする)に約六年勤めた後退社、その後約一年半分(消滅時効の関係から限定)のサービス残業代及び付加金(総額約六〇〇万円)の支払いを求めて提訴したものである。
原告が所属していた職場では、タイムカードが導入されておらず、月末に従業員が申告する労働時間を「調整」した上で労働時間を決定するという扱いが続けられていた(しかも、申告に際しては、被告会社が設けた上限枠を越えることはできないとされていた)。要は、どれだけ残業をしても、被告会社が認める範囲内でしか時間外手当は支払われないという扱いがされており、原告が抗議の上退社した後も、このような扱いは続けられていた。
2 私の問題関心
(1) 最近、「サービス残業」についての報道を頻繁に見かける。トヨタ・シャープなどの大手企業に労基署から勧告がなされたとの報道がなされていたが、二〇〇二年一二月には「約一年半の間に六一三社が総額八一億円余を支払っていた」との厚生労働省のまとめが報道された。さらに、二〇〇三年一月九日、大阪労働局が消費者金融大手「武富士」を労働基準法違反(労使協定の範囲を超えたサービス残業)の疑いで家宅捜索したとの報道があった(同月一〇日毎日新聞等)。ついに強制捜査にまで至ったか、と、感慨深かった。 (2) サービス残業には、法的には、①民事的責任、②刑事的責任(「六箇月以下の懲役または三〇万円以下の罰金」労基法一一九条一号)を負うべきという問題が含まれている。が、この問題に触れるようになって感じるようになったのは、働いている人本人・家族の生活に関わる、極めて深刻な問題であるということである。
冒頭で記載した事件を提訴するにあたり、原告ご本人が毎日の出社・退社時間を記録しておられたスケジュール帳をもとに、過去二年間分の「時間外労働表」を作成してみた。それによると、徹夜が三日、休みは二日という月があったりで、その過酷さには想像を絶するものがある。
また、二〇〇二年一二月七日に行われた「全国一斉労働相談ホットライン」でも、三重県から「サービス残業を何とかしてほしい」という相談があった。運送業に勤める夫を心配した奥さんからの相談だったが、「どこに行っても取り合ってくれない。家族の生活も仕事の責任もあるし辞めてもらえない。私はこのまま夫が過労死するのを待つしかないのか」と、たたみかけるように話されていた。
(3) 前述した報道に触れるたび、このような本人・家族の生活に関わる問題を思い、社会問題化していることに意義を感じつつ、やるせない思いを抱いている。
3 訴訟への思い
(1) 今は、サービス残業の問題を、前述したように本人・家族の生活に関わる深刻な問題として捉えているが、訴訟を提起する前の準備段階では、正直そのような深刻な問題としては捉えていなかった。「働いた分だけの対価を求める」という、当たり前だが実現されていない大事なことを実現するための訴訟、と、比較的ビジネスライクにとらえていた。
(2) そのような認識が改まったのは、提訴当日の記者レクで原告の方の発言を聞いた時である。「毎晩のように深夜まで残業を強いられ体を壊した。今でも体は万全ではない。このまま働き続けると死んでしまうと思った」と、淡々と話された。恥ずかしい話であるが、私は、この時初めて原告の方の提訴に至る思いを聞いた。そして、今回の訴訟が、ビジネスライクな問題ではなく、働く人の健康・いのちに関わる深刻な問題であることを痛感させられた。
(3) 私と同世代の会社勤めの友だちにも、「サービス残業は当たり前」と言いつつほとんど毎日深夜まで働いている人が多い。「体を壊しそう、過労死しそうとは思うけど、仕事にやりがいがあるから続けたい。辞めるわけにはいかない。一人だけ残業を拒否して帰れるわけがない」と、彼らは言う。おかしいと思いつつ現場では何ともできない、というのが、私にとってのサービス残業問題である。 「父は死ぬために働いたのではありません。」というのは私の友人(高校時代父親を過労自殺で亡くされた方)のことばで、このことばを思い出すたびにやりきれなくなるが、このまま「サービス残業は当たり前」な状況が続いていくと、結果的に「死ぬために働いていた?」と思わざるを得ない状況が、数多く生じてしまうのではないだろうか。
このような「サービス残業は当たり前」という状況に警鐘を鳴らすものとして、本訴訟の意義は極めて大きいと考えている。
4 提訴後の動き
原稿執筆時は答弁書待ちである。訴状で、実労働時間を原告の方のスケジュール帳をもとに計算しているため、被告がその実労働時間を素直に認めてくれるとは思えず、実労働時間がどうだったかが中心的争点になると思われる。
一方で、被告会社内ではすでに変化があったそうである。提訴直後、原告の方が所属していた部署では、「残業時間をきちんと申告するように」と言われるようになり、前述した「申告」「調整」という労働時間の把握方法の変更に向けた動きが見られるという。勝訴を目指し全力を尽くすのは当然であるが、その過程で、被告会社にとどまらず、サービス残業問題解決に向けての、大きく確実な一歩一歩を作っていけたらと思っている。
二 おわりに
私事であるが、本訴訟は、私が二〇〇二年一〇月に弁護士登録した後初めて訴状を作成し提訴にまで至った、私にとっての「弁護士第一号事件」である。訴訟内外全ての事が新鮮で、自分の未熟さを痛感させられる。様々な出会いを大事にしながら、精一杯取り組んでいきたい。
2003/02/01