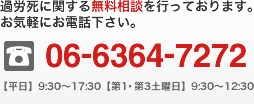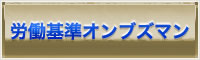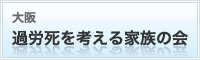新認定基準の適用によって申請から約一年で労災認定─運送会社運転手Sさん事件─ 弁護士 原野早知子(民主法律252号・2003年2月)
弁護士 原 野 早知子
一 初めてこの事件の相談を受けたのは、私が東大阪市の民商に法律相談に行った時だった。民商の法律相談で過労死の案件が来ることなど珍しいので、よく覚えている。
被災者は、Sさん。Tグループの運送会社(T運輸株式会社)で、運行管理を主として担当し、運転手の手配が間に合わない時には自分もトラックを運転するといった事務兼運転の業務に従事していた。平成一三年七月一二日、夜勤中に倒れ、脳幹出血で、翌一三日に死亡している。奥さんとまだ四歳の男の子が残された。
私が相談を受けたのは、Sさんの死亡後間もない、暑い時期であった。
奥さんの話では、「会社からは、『ご主人は病気で死んだのです』と言われ、労災申請にとりあってもらえない」ということだった。しかし、奥さんが持参した手帳には、かなりの長時間労働を示す労働時間が、死亡したSさん自身の手で書き込まれていた。
私は、労災の申請や会社への損害賠償といった方法があること、タイムカード等の資料を入手するためには証拠保全が必要になるかもしれないことなどを説明し、継続して相談を受けることにした。
とはいえ、私自身は過労死事件の経験が少なく、集団で取り組む必要を感じたので、当時一緒に溶接工の為実過労死事件を担当していた岩城弁護士に弁護団配置について相談した。岩城弁護士曰く、「そういうときにはね、今やっている弁護団をそのままスライドさせる、ということをよくやるんだよ」。それで、為実過労死弁護団(岩城・村瀬・有村各弁護士と私)でそのままこの事件を担当することになった(ただし、私が他の弁護士から聞いた話によると、「そんなやり方は聞いたことがない」ということであったが)。結果から言うと、この弁護団配置は私にとっては大変やりやすかった。為実事件は既に平成一〇年から取り組んでいる事件で、弁護団の中でお互い気心が知れているし、一方の事件の打合せをしているときでも、もう一つの事件の相談をしたりすることができるからである。また、既に為実事件でメーリングリストを作っていたが、S事件でもメーリングリストを作って、事務所の異なる弁護士四名の連絡がスムーズにできるようにした。
・・・・こんなことは余談かもしれないが、本件で業務上認定を早期に勝ち取れたのは、弁護団を早急に結成して作業を行ったことが一つの要因といえるので、弁護団配置の事情や工夫を少し紹介した次第である。
二 平成一三年九月に入り、弁護団四名と遺族で今後の方針について打合せを持った。
私は、この時まで、ほとんど為実事件しか経験がなかった。為実事件では、証拠保全のうえ、労災申請と会社に対する訴訟提起を同時に行っていたので、S事件でも同様の方法を取るのだと思っていた。
しかし、話を聞いてみると、打合せ時までに、遺族と会社が話をしており、遺族が労災を認めようとしない会社の姿勢に怒ったところ、会社側は労災申請に協力すると言っているという。
そこで、いきなり会社に訴訟提起して対決姿勢をとるより、会社の協力を求めながら、労災申請を先行していくという方針を取ることになった。
このため、タイムカードや勤務記録、健康診断票などの必要な資料は、証拠保全をせず、会社に弁護団から問い合わせをして、コピーを取り寄せた。その結果、労働時間については、タイムカードと「乗務記録カード」(常に乗務していないSさんについても毎日の勤務時間が記録されている)を約一年分確保することができ、Sさんの労働時間を確定することができた。Sさんの手帳に記載された労働時間も、抜けている期間があったりしたため、タイムカードや乗務記録カードで補い、これらを整理して、信用性の高い労働時間の一覧表を作ることができた。
Sさんの業務内容や勤務ぶりについては、遺族が元の同僚に連絡し、一○月に弁護団(岩城・村瀬・原野)が、同僚三名から、詳しく話を聞く機会を設けることができた。同僚の皆さんは、皆会社で勤務を続けている身だったが、快く話をしてくれた。これによって、Sさんがしていた仕事の内容を明確にすることができた。
また、奥さんからも詳細な聴き取りを行い、有村弁護士が力の入った陳述書を作成し(有村弁護士の事務所総出で、業務時間と睡眠時間の一覧表をカラーで作成)、発症前一〇日間余りの特に苛酷だった勤務状況を明らかにする資料になった。
三 Sさんはもと運転手だったが、真面目な人柄を買われて、駐車場(集配場)での運行管理業務に配置された。点呼業務や運転手への配車業務(配送先毎に担当運転手が決まっているが、担当運転手が休みの時や荷物が積みきれない場合に代わりを手配するなどの業務)、荷物のトラックへの積み込み業務、電話応対・クレーム対応、伝票整理などに従事していた。配車業務で手が足りない時には、Sさん自身が運転をすることもあった。運送する物品は自動車の精密な部品であり、積み込みや運転には、大切な部品を傷つけないよう、細心の注意が必要とされる。
また、トラックは夜でも走るため、Sさんの業務は、日勤と夜勤が一週間交替の交替制勤務であった。日勤は午前八時三〇分から午後七時までの一〇時間三〇分勤務、夜勤は午後七時から翌朝七時まで(日曜日のみ午後一〇時開始)の一二時間勤務である。そもそも所定の労働時間が八時間を超えている。休憩時間は一時間とされていたようだが、電話(「荷物が届かない」等の苦情が多く、クレームがあれば担当の運転手に連絡を取るなど対応が必要となる)が、いつかかってくるか分からないので、まとまった休憩を取ることはなかなかできなかった。特に夜勤の場合は一人勤務なので、一応仮眠を取ることはできるが、電話が鳴れば起きなければならない体制にあった。
仕事が時間外にずれこむことも多かったようで、タイムカードの記録では、会社に提出する「乗務記録カード」より、一時間以上(多い時には二時間)労働時間が長い場合もあった。
Sさんはやや肥満体質ではあったが、このような恒常的な長時間労働、定期的に繰り返される長時間の夜勤勤務による不規則労働が疲労を蓄積させていったことが、脳幹出血発症の根底にあると考えられる。
Sさんが発症する前の約一〇日間の労働は、特に厳しいものだった。Sさんが倒れた七月一二日は夜勤の週で、その前の週は日勤だったところ、七月三日から六日まで四日連続、普段の配車業務ではなく、トラック乗務の仕事だった。しかも、この四日間の拘束時間(労働時間)が異常に長い。
七月三日には午前〇時から一九時間配送業務に従事し、翌七月四日には午前五時半に起床し六時過ぎに自宅を出て、配送業務に従事、その後一旦帰宅してから再度午後一〇時二〇分に自宅を出ている。荷物が積みきれず、急きょ応援で運転業務に従事することになったためで、このため、七月四日の午後一一時七分に出勤のタイムカードを打刻して出発、七月五日は〇時から午後六時三〇分まで一八時間三〇分配送業務に従事した。この時、トラックのエアコンが故障しており、Sさんは異常な暑さの中をクーラーなしで運転業務に就き、滅多に愚痴などこぼさない人なのに、帰宅してから、「故障しているならもっと早く知らせて欲しかった」と妻に話していた。その疲れもとれないまま、翌七月六日にも午前五時三〇分に会社を出発し、長野県松本市へ日帰りの乗務勤務をし、労働時間は一八時間に及んだ。発症直前のこの四日間の苛酷な業務が、Sさんを過労に追い込み、体調を更に悪化させたと考えられる。
Sさんは、それから間もなく、七月一二日、一人で夜勤に従事している最中に倒れたのだった。
四 このような実状を把握し、弁護団は、平成一三年一一月末には労基署へ意見書を提出すべく作成作業を進め、ほぼ完成に近づいていた。ところが、ちょうどその時期に、過労死の認定について、厚生労働省が認定基準の見直しを行い、新認定基準が一二月には通達で示されることになった。
当然、馬場さんの事件についても、認定は新基準で行われることになる。そこで、弁護団では、再度、新認定基準に合わせて、事案を洗い直した。
その結果、Sさんの労働時間は、会社に提出した「乗務記録カード」を前提としても、時間外労働が死亡前一か月間で一〇〇時間を超えており、不規則勤務・拘束時間の長い勤務にも当たっており、明らかに新基準に当てはまるものであることが判明した。
そこで、意見書の内容としては、新基準を取り入れ、①死亡直前の苛酷な業務を中心とする「短期間の過重業務」(従来の基準)への該当性と、②死亡前1か月の業務を中心とする「長期間の過重業務」(新基準)への該当性を2本柱として主張することにした。この方針に基づき、意見書を書き直し、年が明けた平成一四年一月、労基署へ資料とともに提出した。この時には、弁護団と奥さんが北大阪労基署へ出向いて、意見書の内容説明を行った。
労基署の方でも、他にも事件が累積しているということであったが、本件は明白な事案なのだから、早く調査をして結論を出して欲しい、と何度か電話で督促を行った。
Sさんが亡くなったのと同じ暑い夏がめぐってきて、過ぎていこうとする頃、ようやく、労基署から奥さんのもとに通知が届いた。平成一四年九月一〇日付での労災年金・一時金支給決定だった。私にとっても、弁護士になって初めてとった業務上認定だった。
五 本件では、被災者の発症・死亡後すぐに労災申請を行い、約一年余りという比較的短期間で労災認定を勝ち取ることができた。このような成果を得られた要因はいくつかあると考えられる。
まず、被災者であるSさんの労働時間をほぼ一〇〇%把握でき、それが新認定基準に照らして、業務起因性を認められる「死亡前一か月に時間外労働一〇〇時間以上」に明らかに該当していたことである。新認定基準は、労働時間のみで形式的な判断がなされる問題点をはらんでいる。しかし、新基準への該当性が明らかな事案では、一方に肥満等の傾向(素因)があっても、業務上認定を行わせるものであることが、本件では後押しとなった。
二番目には、会社側が労災申請について比較的協力的であり、資料提出もスムーズに行い、同僚からの聴取を妨害するような姿勢をとらなかったことである。弁護団は会社の大阪支店にも協力依頼(挨拶)に行ったが、そこでも対応は好意的であった。最初から訴訟に持ち込むような方針をとらず、会社に協力を求めた方針が成功したといえる。
三番目には、被災者の死亡からすぐに調査を開始したため、家族を含め関係者の記憶も鮮明であり、事実関係を正確に把握できたことがある。おかしいものはおかしいと考えてすぐに労災申請を決意した奥さんの勇気が早期の認定につながったといえる。また、もちろん、Sさんの真面目な仕事ぶりがあったからこそ、同僚の協力も得られたものである。
四番目には、手前味噌ではあるが、弁護団がよく協力し、早めに意見書を提出することができたことも挙げてよいと思う。労災案件では、裁判と異なり期日がないので、ついつい仕事を後にのばしがちであるが、本件では、労基署への提出時期を決め、それまでに必ず完成させるという方針を貫徹した。業務内容に正確を期すため何度も同僚に電話をかけた村瀬弁護士、先にも書いたが、奥さんから詳細な聴き取りを行い、誰が読んでも苛酷さを実感せずにはいられない陳述書を完成させた有村弁護士、適切な方針を立て労基署への督促でもベテランの味を発揮した岩城弁護士、この協力体制あってこその早期認定であったと思う(私は労働時間の整理を担当した)。
六 会社には、労働災害の場合に三五〇〇万円の附加金が支給されるとの労使協定があった。現在は、これに加えて、Sさんの損害の上積み保障を求めて、会社と交渉中である。
会社が労災申請に協力的であっただけに、今度は相手方として交渉するのも難しいところがあるが、最後の解決まで後少しなので、頑張りたいと思っている。 (弁護団は、岩城穣・村瀬謙一・有村とく子・原野早知子の四名)
2003/02/01