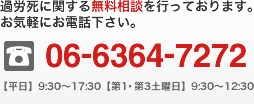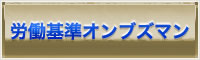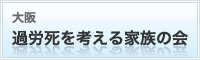小学校の先生に、過労死は認められないのか。──公務外の鈴木教諭公務過労死── 弁護士 村田浩治(民主法律226号・1996年2月)
弁護士 村田浩治
一 鈴木先生の死に公務外認定
堺市立新金岡小学校でクラス担任を持ち、体育主任、保健主事を兼ねていた鈴木先生が帰宅途中で倒れ亡くなったのは、1990年の10月だった。
ただでさえ忙しい鈴木先生だったが、この時期は、連合運動会、学校運動会、遠足、社会見学と行事が重なった時期で、天候不順のため計画が往い、非常に予測のたちにくい中で先生たちの負担感の増していた時期でもあった。
もともと、鈴木先生が、多忙を極めていたことば、皆か知っていたから、同僚の多くか鈴木先生の死は過労死だと考えて、同じ堺市の小学校教員である奥さんを励まして公務上災害の認定を求めて地方公務員災害補償基金大阪支部に認定を求めてから丸4年が経過した。この間、担当者は2回交代したが、長期に渡る同僚からの調査等を踏まえた結論が本年1月12日に示された。結論は「公務外」つまり、公務とは関係のない発症であるというものだった。
二 事件の概要
故鈴木均先生は、堺市立新金岡小学校の5年生の担任をしていた。1990年の10月8日、帰宅途中に立ち寄ったローソン前で頭から血を流しているのを発見された。当初は刑事事件発生かと思われたが、脳梗塞のため転倒したことが分かった。
鈴木先生の公務の過重性を一言で述べるのは難しい。もともと、5年生という年頃の難しさに加え、まだ甘えを求める児童や困難児童も一様でなくアレルギーなとさまざまな問題を抱えているクラス担任であり、負担は多かった。
さらに体育主任として、学校の運動会の実施のための練習時間の調整、雨天のための順延に、さらに調整が必要となり、さらに時間をとられていた。また連合運動会という堺市の小学校が集合して行う大運動会の組体操の指導など独自の精神的負担があった。
教育委員会で本来兼任を避けるよう指示されていた保健主事という役職にもついていた。
他に入力できる人がいなかったため学校行事のしおりや計画書を統一のワープロに写すために再入力作業もしていた。
鈴木先生の死を聞いて、多くの同僚が、こうした事実を語り、鈴木先生の死は過労が原因であると訴えていくため「鈴木均先生の公務災害の認定請求をすすめる会」が結成され、同僚だけでなく教職員組合や地域の父母たちも加わった運動が徐々にではあるが広がっていった。
学校数諭の公務の過重性は、こうした証言か集められてもなかなか立証できない。多くの先生同様、鈴木先生の公務も時間で管理されているわけではない。熱心な先生は無定型の公務か増加していくことは間違いないか、それを一つ一つ立証していくことは極めて困難である。
しかし、運動の広がりは、当時の子どもたちからも鈴木先生の様子が、当時おかしかった事(チョークをよく落とす)なども発掘した。運動会当時、前年に器具のいたずらなどかあっため父母たちと協力して見回りを強化していたことなども分かった。
こうした運動の広がりの中で公務災害補償基金がどのような評価を下すかが注目されていた。
三 納得でき難い認定の理屈
1 複数の担当者がいれば、1人への公務過重はない
基金の決定はさすがに鈴木先生か当時、様々な行事に追われていた事は認めざるを得なかったが、こうした行事は、多くの担当教諭と協力して行っており鈴木先生1人だけが負担していたものでないとして、公務過重性を否定している。
しかし、体育主任として関わっていた事実をどのように評価するのかは明らかでなく、任務分掌で複数の担当者がいれば負担がないとして、当該被災者の負担の状況を検討していない。何のために、長年調査をしていたのか。
2 持ち帰りは認めながらも成果物がなければ残業は認定しない
当時、学校行事が立て込んでいたため、持ち帰り作業は認めざるを得ないことまでは認定したが、結局、成果物かないこと、そのため持ち帰り残業の内容を特定できないとして、この認定を放棄した。同僚や妻が、行事の経過からみて、この時期には、この持ち帰り残業をしていたと認定できるとする資料を提出しているに、これに対してはコメントを加えていない。
3 すでに発症しながら公務についていたことを認め「公務外」の理由に
また、理由書は、最後に「チョークをよく落とすなど当時、すでに発症していたと思われる」とした上で、それより1週間以上前は特に行事もなく過重性はなかったことを理由にして病気か自然的経過の中で発症したとしている。
しかし、公務についていた当時に発症していたことを認めながら、この病気を押して公務についていたという事実があるならば公務が疾病を悪化させたとの認定も十分あり得るところである。こうした理由付けから見ると基金は端から公務外の認定をする前提であらゆる事実を評価しているといわれても仕方がない決定をしたのである。
※ なお、この原稿を書いているのは認定が出た直後であり弁護団全体での検討を経ていないが認定の理由を読むだけでざっと以上のような問題点が指摘されると執筆者の判断を記している。
四 基金支部審査会に向けて
決定が公務外となることは十分に予想されたことである。これまで基金支部の段階で公務認定されているケースは学校教師の脳心臓関連疾患ではほとんどない。
事務職やサービス業種の過労死の関連の認定が増加している中でこの決定は覆していかなければならない事件と考えている。過重性の主張の重点をどう絞るか、今後の認定を進める運動の再構築が課題となっている。(弁護団は他に松丸正、峯本耕治、赤津加奈美、阪田健夫)
(民主法律226号・1996年2月)
1996/02/01