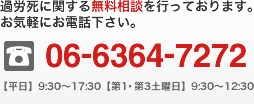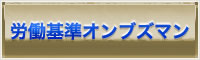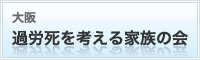家族の会の活動について 大阪過労死を考える家族の会事務局 池田憲彦(民主法律226号・1996年2月)
大阪過労死を考える家族の会
事務局 池田憲彦
はじめに
「大阪過労死を考える家族の会」(以下、家族の会)が結成されたのは、1990年12月8日のことで、昨年の12月で満5周年を迎えました。その結成総会には会場いっぱいに約60人(家族会員28名、賛助会員33名)ほどの人が集い、たくさんのマスコミ関係者も集まり、涙、涙の集会だったそうです。
〝そうです″というのは、私自身は会の結成当時は、家族の会の運動にはまだ加わっていませんでした。それどころか、過労死問題には実際には何の接点もなく、世の多くの人たち同様、〝過労死″というのを、現代社会を表現する枕詞の1つ程度にしか知らなかったのです。
私自身が賛助会員として、この会の事務局の仕事をお引き受けしたのは、過労死問題を真正面から訴えたお芝居「突然の明日」の上演運動にたまたま加わったこと、そしてそのことを通じて平岡事件を知ったことからでした。それからこの3月で早3年がたとうとしています。私にはその2年間のことしかわかりませんか、家族の会のこの2、3年間のとりくみのあらましと現状をこの紙面をお借りしてお伝えしようと思います。
1 家族の会の目的と活動内容
家族の会は、「過労で倒れた本人と家族のために労災認定並びに企業補償の拡大に取り組むとともに、過労死の発生を予防するための諸活動に取り組む」 ことを目的にしながら、
① 被災者・家族・過労死問題に関心を持つ人の交流の場をつくり、過労死の問題を広く社会的にアピールしていく。
② 過労で倒れた本人と家族の労災補償の改善と企業補償の要求に取り組む。
③ 過労死の発生する社会的背景について、その問題点を明らかにし、過労死の発生の予防に取り組む。
ことを実際の活動内容としています。
約3年前に、ほぼ現在の世話人と事務局の体制になったとき、上記をさらに具体化して.活動の3つの柱として、当時の総会で次のように申し合わせています。
(1) 過労死問題の本質や背景、労災認定問題などを学習し、それぞれの生活と運動に役立てる。
(2) 家族同士、あるいは他の分野でたたかっている人たちとの交流を深め、絆を強める。
(3) 過労死問題を広く社会に知らせ、世論を喚起する。
すなわち、要約的にいえば、「学習・交流・社会的アピール」を3本柱に、活動しているわけです。
2 この2、3年間の活動について
(1) 文化をつうじてアピール
不十分ながらも上記の3つの柱にそって活動してきた3年間でしたが、その最初の2年間は、過労死問題を〝文化″をつうじて社会 に訴えるということが取り組みの中心になりました。
1993年11月には、「家族とともに過労死を考え、交流する文化の夕べ」を開催しました。ここでは被災家族の中の音楽家(亀井祐子さん、平岡友子さん)の声楽とピアノ演奏を中心に、フォークグループやプロの声楽家も招いてコンサートをしました。また関西勤労協の中田進先生に講演をお願いしました。会場はほぼ満員になり、200名近くの人たちの参加があり、幸いこのコンサートは多くの人の胸をうつ感動的なものになりました。
翌1994年12月には、今度は東京から招いたプロ歌手の佐藤真子の歌と大阪教育大学助教授、木田淳子先生の講演でやはり「文化の夕べ」を行いました。前の年の成功の余勢をかって、「今度はもっとおおきな規模で」と意気込んで堺市の400人以上収容できるサンスクエア堺で取り組んだのですが、実行委員会の力不足のため100名あまりの参加者しか集めることかてきませんてした。しかし、いずれの会場でも被災家族が参加者に、「過労死問題に関心をもち、家族に協力してほしい」と心から訴えました。(1993年は仮屋さん、1994年は新田さんが代表してあいさつ)
集いのもち方などはもっと工夫がいるかも知れませんか、こうした文化をつうじて過労死問題を知らせていくことは時として今後も有効な1つの取り組みではないかと思っています。
(2) 家族同士の交流という〝原点″にかえって
それまでの取り組みも、当然家族会員の意見を聞きながらすすめてきましたが、2回目の「文化の夕べ」の総括をする中で、どちらかというと事務局主導型になっているのではないかという反省も出てきました。また 「文化の夕べ」は内容的にもややイベント的な色合いか強いのも気になりました。「必ずしも家族会員の要求に全面的に沿いきったものになっていないのでは…」という思いでした。
そこで、家族会員の方に何を「家族の会」としてやっていきたいか改めて意見を求めました。すると「もう一度世間の人達に訴えてみたい」ということと、「家族会員同士の交流をもっとしたい」という2つが出されました。
翌1995年は、1994年8月に再刊した家族の会ニュース(「ともしび」と命名)を継続して発行することと、交流の活動に力を入れるようにしました。 そういうわけで世話人(家族会員)と事務局の合同会議で相談してもったのが、久しぶりの6月の例会でした。
土曜日の夕方、天満橋のあい粂という少し鄙びた旅館に総勢21名が集まりました。まず夕食をともにした後、家族の会にとってもおなじみの中田進先生から、過労死を生みだす日本の社会のしくみなどについてお話を聞きました。そしてその後全会員発言の交流をゆっくりおこないました。
紙数の都合でその交流の内容は省略しますが、この例会はその後、家族会員同士のネットワークを広げ、深めていくことにかなり役立ったようです。というのは、最近審査官の段階で認定を勝ち取られた仮屋さんが、審査官交渉の最終局面を迎えられ必死の取り組みをされているところでした。その仮星さんの要請に応えられ、それまで以上に家族会員の方々が、審査官交渉についていかれるようになったのです。その連絡を取り合いながら家族会員同士、悩みを出し合ったり、励まし合ったり、アドバイスかされたりしたようです。
これは本来の家族の会の大切な存在意識の1つであり、これまでもそれなりに自然と行われてきたことではありましたが、事務局の立場で見ていて、この例会を期にいっそうそうした活動かつよまったように思うのです。
そんな中で、1994年11月に開かれた関西の学生さんによる過労死問題のシンポジウムのときに初めて参加された三田のSさんが、もともとあった「夫は過労死で亡くなったんだ」という自らの確信を形にして、いよいよ労災申請に取り組まれることになったことなど、この1年間の活動の大切な成果だと思っています。
3 今後の家族の会の在り方
仲間が増えるとうれしいんだけれど、一方で複雑な心境にもなるというのが「家族の会」です。そして私たちはいつも語り合っているのてすが、この会はいつかなくなることを目標にしている会でもあります。しかし、残念なから会にお誘いしようと思う人は後を絶ちません。
会としてやりたいことは、実はまだいくらでもあります。もう一度原点に帰って、過労死の個々の事件を被災家族が人々に伝えること、労災の認定をなんとしても勝ち取ろうという家族会員への支援、労働省や企業への働きかけや、自治体に過労死の認定基準の見直し決議を上げてもらう要請行動、「全労連」や「連合」など組合への要請活動、過労死問題そのものを広く社会の人々に知ってもらう取り組みなどなどです。
昨年秋の総会で新しい世話人も選ばれ、4人の事務局とともに新しい年を迎えました。数年前には平岡チエ子さんと岩城弁護士と2人で会議をされていることもありました。家族を過労死で失った家族会員はそれでなくても、まず例外なく生活に追われることになります。そして認定のためのたたかい、企業責任の追及と、自分の事件のことでいくらでもしなければならないことが出来てくるのです。そんな中での家族の会です。
これからも被災家族にとって心強い心の依り所であり、認定を勝ち取ろうとする人のネットワークであり、社会に向かっては過労死の廃絶を心から訴えるメッセンジャー集団である、そんな家族の会をみなさんとつくっていけたらと考えています。みなさん、引き続きあたたかいご支援をお願いします。
(民主法律226号・1996年2月)
1996/02/01